実は、わたくし今までほとんどフレームワークらしいフレームワークは使ったことがありません。
さすがに、そろそろフレームワークでも触ってみようかと思って色々調べました。
一応この業界に10年ほどいるんですけど、僕の周り(大手SIや協力会社)などで圧倒的に使われているのが、未だにStrutsなんですよね。
でも、今からStrutsかーと思って色々調べたところ、Playframework2というフレームワークが非常に人気らしいので、インストールしてみました。
Playframework2のダウンロード
下のページのリンクから、最新の公式バージョンをダウンロードします。
Download — Playframework
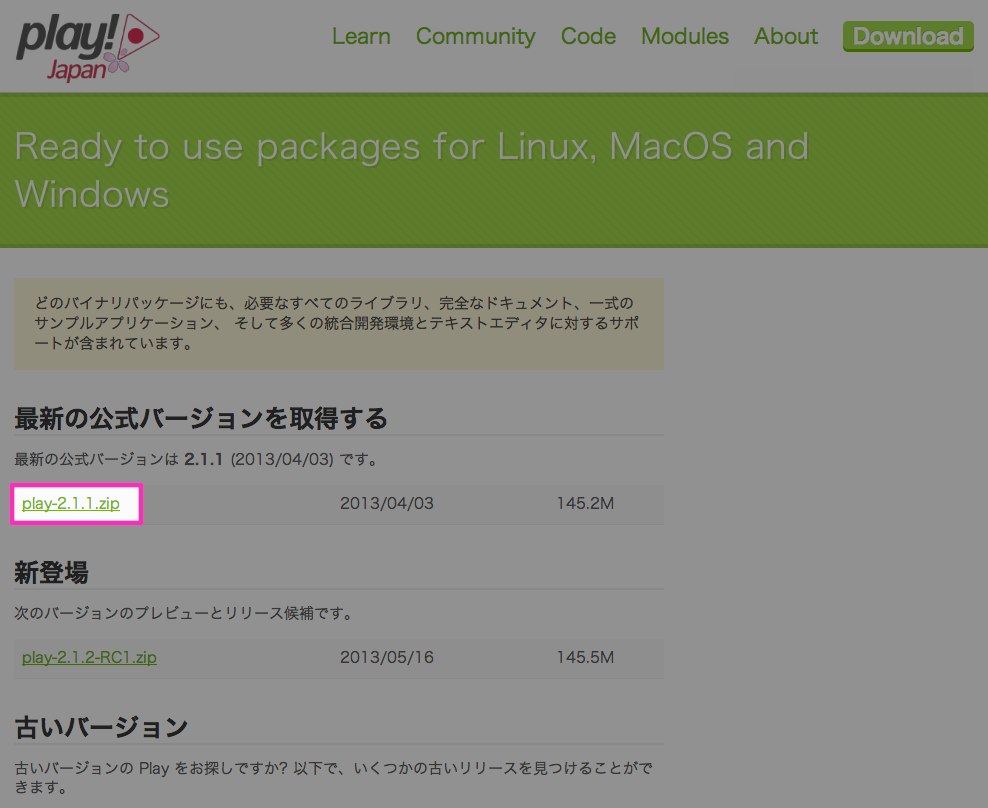
ファイルサイズは100MBくらいあるので、時間がかかる場合があるかもしれません。
Playframework2のインストール
zipなので適当に解凍してインストールします。
イマイチどこにインストールしたらいいのかわからないのですが、僕はホームディレクトリにToolsというディレクトリを切って、そこに色々配置しているので、今回もそこにインストールしました。
[bash]
mkdir -p ~/Tools/play
mv play-2.1.1 ~/Tools/play/2.1.1
[/bash]
もちろん、こんなところにパスなんて通っていないので、パスを通します。
僕はzshを使っていますが、みなさまのログインシェルに合わせてください。
[bash]
vim ~/.zshrc
# 末尾に追加
PLAY_HOME=/Users/自分のユーザ名/Tools/play/2.1.1
export PLAY_HOME
PATH=$PATH:$PLAY_HOME
export PATH
[/bash]
で、最後にパスが通ったか確認します。
[bash]
which play
[/bash]
playまでのパスが表示されればOKです。
play not found
みたいに表示されたら、多分パスの設定が違っています。
Playframework2を起動してみる
とりあえず、最初のアプリを作ってみます。
どうせ消すつもりなので、デスクトップで作業。
[bash]
cd ~/Desktop
play new sample_app
# ここで色々ダウンロードが始まります。
# アプリケーション作成の質疑応答になります。
What is the application name? [sample_app]
> (エンター)
Which template do you want to use for this new application?
1 - Create a simple Scala application
2 - Create a simple Java application
> 2(エンター)
OK, application sample_app is created.
Have fun!
[/bash]
ってな感じで、表示されたらOKだと思います。
多分、アプリケーションのひな形が作成された状態だと思います。
では、起動してみましょう。
[bash]
cd sample_app
play run sample_app
[/bash]
起動したら、ブラウザを開いてlocalhost:9000にアクセスします。
Playframework2のサンプルページが表示されれば、無事起動完了です。

とりあえず、今回は起動までしましたが、次回以降は少しアプリケーションを作ってみたいと思います。